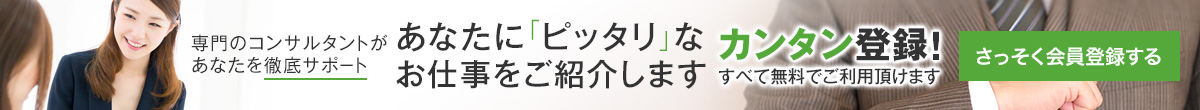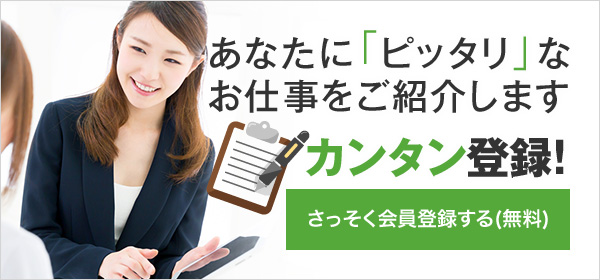忙しいドクターのための会計税金3分講座医療業界に精通した
ジャスト会計事務所の代表者ブログ
- - 開業医・医療法人 -
すべてのドクターのための
税務関係パーフェクトマニュアル -
 立野 靖人[公認会計士/税理士]
立野 靖人[公認会計士/税理士]- 昭和56年1月10日生。 兵庫県神戸市出身。
私立甲陽学院中高、神戸大学経営学部を卒業後、大手監査法人勤務を経てジャスト会計事務所設立。
業務で培った貴重な知識や経験を多くの人に伝えたいという思いで、甲南大学の非常勤講師を
務める(現職)。公認会計士登録 第23121号、税理士登録 第115818号。
「法定相続人」と「相続人」投稿日:2013/11/10
前回、相続税が発生する範囲、発生しない範囲をご説明しました。
法定相続人の数に応じて、一定の金額の範囲内であれば相続税は発生しません、 というお話でした。
ここで出てきた「法定相続人」は、あくまで放棄などがなければ相続人になると 法律で規定される人であり、遺産を受け取る「相続人」とは異なる場合もあります。
このあたりが相続のややこしいところで、誤解をされている方もいるかもしれません。
確かに民法上、「法定相続人」の規定はありますが、だからといって 法定相続人だけしか相続できないわけではありません。
被相続人(ご本人)が指定した人も相続する権利を有します。
誰に相続させるかをはっきりさせるため、遺言書などを残しておくわけですね。
実際は法定相続人が遺産相続を放棄することもあれば、 亡くなった方が遺言で法定相続人以外の方を相続人として指定することもあります。
相続についての民法の規定は非常にややこしいのですが、 税法の規定もそれにまけずおとらずややこしいものになっています。
税法上、相続税を計算するには、
というステップを踏むことになっています。
ちなみに、相続税も所得税と同じで累進課税になっているので、 相続人の数は多い方が分散されて課税金額が低くなり、論理上支払う税額は安くなります。
ということは、実際にその法定相続人に相続させるかどうかは別にして、 法定相続人が多ければ多いほど、相続税額が少なくなるという計算結果になります。
直感的に理解しづらい計算方法になっていますので注意が必要です。
なお、今までは非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないとされていましたが、 平成25年9月4日の最高裁判所においてこれが違憲とされ、 嫡出子も非嫡出子も平等に分けること、とされました。
この点についても注意が必要ですね。

 閲覧履歴
閲覧履歴